循環器内科
循環器内科では、主に心臓や血管に関する病気の診断と治療を行っています。
胸の痛み、息切れ、動悸などの症状がある方や、健康診断で心電図の異常や心雑音を指摘された方もご相談いただけます。
心臓疾患が疑われる場合は、必要に応じて詳しい検査を行い、その結果に基づいて状態に合った診療を進めていきます。
「日本循環器学会認定 循環器専門医」の資格を持つ医師が、これまでの経験を活かして診療を担当します。
また、より専門的な治療が必要と判断された場合には、近隣の医療機関をご紹介します。
心臓や血圧に関して気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
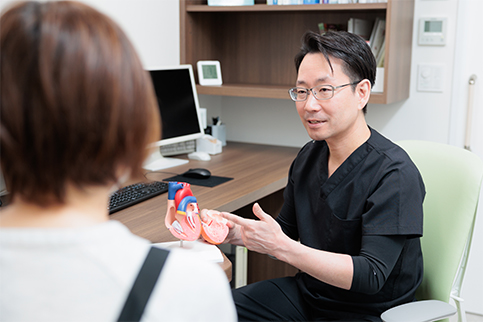
このような症状の方は
ご相談ください
- 心拍数が高くなる
- 脈が乱れる
- 足が腫れている
- 胸の圧迫感がある
- 階段を上る際に息切れする
- 息を吸うと胸が痛い
主な疾患
心臓の病気
心不全
心臓の働きが弱まり、全身に十分な血液を送れなくなることで息切れやむくみが生じる状態です。
狭心症・不整脈・弁膜症・高血圧などが原因となることが多く、症状としては身体のだるさや体重増加も見られます。
心不全の治療では、症状を和らげることと原因に対処することの両方が大切です。心臓の機能が低下することで日常生活に影響が出ることもあります。
心筋梗塞
冠動脈が詰まり、心筋に十分な血流が届かなくなることで、心臓の組織が壊死してしまう病気です。
主な原因は動脈硬化で、狭心症が進行して心筋梗塞に至ることもあります。発症すると突然強い胸の痛みが起こり、放置すると深刻な状態に陥ることがあります。
痛みのほか、冷や汗や吐き気、息苦しさを伴うこともあり、早めの対応が大切です。
狭心症
冠動脈が狭くなることで血流が低下し、胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気です。
初期には目立った症状が出にくい場合もありますが、進行に伴い動悸や息切れがあらわれることがあります。
特に運動や階段の上り下りといった場面で症状が出やすくなります。
糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病が関係することが多く、日頃の体調管理や生活習慣の見直しが大切です。
心筋症
心臓の筋肉に異常が生じることで、血液を送りだす力が弱まり、心機能が低下する病気です。冠動脈や心臓弁に異常がない場合でも発症し、不整脈や心不全の原因となることがあります。
遺伝的な背景が関与することもあり、若い世代でも見られるのが特徴です。動悸や息切れなどの症状が出現し、生活に支障をきたすこともあります。原因が特定できない場合もありますが、全身の病気やウイルス感染、過度な飲酒が影響することもあります。
弁膜症
心臓の弁は血液の流れを調整し、逆流を防ぐ役割があります。
この弁が傷むと、血液が逆流する閉鎖不全症や、開きにくくなる狭窄症が起こります。加齢による変化が原因となることが多いですが、感染症や先天的な要因によっても発症することがあります。
初期は自覚症状がほとんどありませんが、進行すると胸の痛みや動悸・息切れ・むくみなどがあらわれ、日常生活に影響を及ぼすことがあります。
不整脈
不整脈にはさまざまな種類があり、脈が速くなるものや遅くなるもの、一時的に心臓が止まったように感じるものなどがあります。
運動や緊張によって一時的にあらわれる場合もあれば、心臓の病気などが背景にあることもあります。
主な症状としては、動悸や息切れ、めまい、ふらつき、胸の痛みなどがあり、状態によっては失神を引き起こすこともあります。
気になる症状がある場合は、早めの受診が大切です。
血管の病気
大動脈瘤
大動脈の一部がこぶのように膨らんだ状態を指します。
動脈硬化や高血圧、脂質異常症・糖尿病などが関係していることが多く、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし、こぶが大きくなると破裂のリスクが高まり、胸や背中、腹部に痛みが生じることがあります。
発生部位によって胸部大動脈瘤や腹部大動脈瘤などに分類され、進行すると治療が必要になることもあります。
閉塞性動脈硬化症PAD
足の動脈が狭くなったり閉塞したりする病気で、血流が悪化することによりしびれや痛みが生じます。
進行すると潰瘍や壊死の危険があります。
生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)・喫煙・肥満・加齢が原因となり、特に喫煙は末梢の血管を収縮させるため、発症リスクが高くなります。足の痛みや冷え、しびれ、歩行の際の痛み、傷が治りにくいなどの症状があらわれます。
高血圧症
医療機関で測定した際に、最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上で診断されます。正常値は、最高120mmHg未満、最低80mmHg未満です。
高血圧は自覚症状がほとんどないため放置されがちですが、血管に負担がかかり、動脈硬化が進行します。
動脈硬化が進むと、心筋梗塞や脳梗塞などの重い病気を引き起こす可能性があります。
検査方法
心電図検査

不整脈や狭心症の診断に役立つ検査で、身体に電極を取り付け、心臓から発生する微弱な電気の変化を波形として記録します。
また、携帯型の小型心電計を装着し、日常生活を送りながら24時間の心電図を記録する方法もあります。
短時間の測定ではわからない心臓のリズムや異常を詳しく確認でき、心筋梗塞・不整脈・心筋症・心筋炎など、さまざまな心疾患の診断に役立てられています。
ABI検査

血管の状態を調べる検査で、動脈硬化の進み具合を血管年齢として確認できます。両手足の血圧を測定し、ABI(足関節上腕血圧比)を算出することで、閉塞性動脈硬化症などの重症度を評価します。
検査時間は約5分です。動脈硬化は加齢だけでなく、食生活や運動不足・高血圧・糖尿病・喫煙などが影響します。進行すると脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まるため、早期の確認が大切です。
